コロナや、関税、予期し得ない変化が常態化している時代。どのように生き抜いていけばよいのだろうか?失われた30年といわれる日本。それを片目に成長を繰り返す海外企業。どこに差があり、我々はどのように生きていけばよいのだろうか?今回は様々なリーダーシップ論が世の中にありますが、今の時代に合ったリーダーシップとは何かをまとめました。
不確実な世の中で生きる企業
不確実な世の中で良く伸びていくために必要な要素は次の2点
1.Stability(経営の安定性)
2.Innovation(イノベーション)
それでは2025年現在の、日本企業と世界の企業を比較してみましょう。今回はわかりやすい自動車産業で。
テスラを抜いてBYDが1位。トヨタは7位という結果。
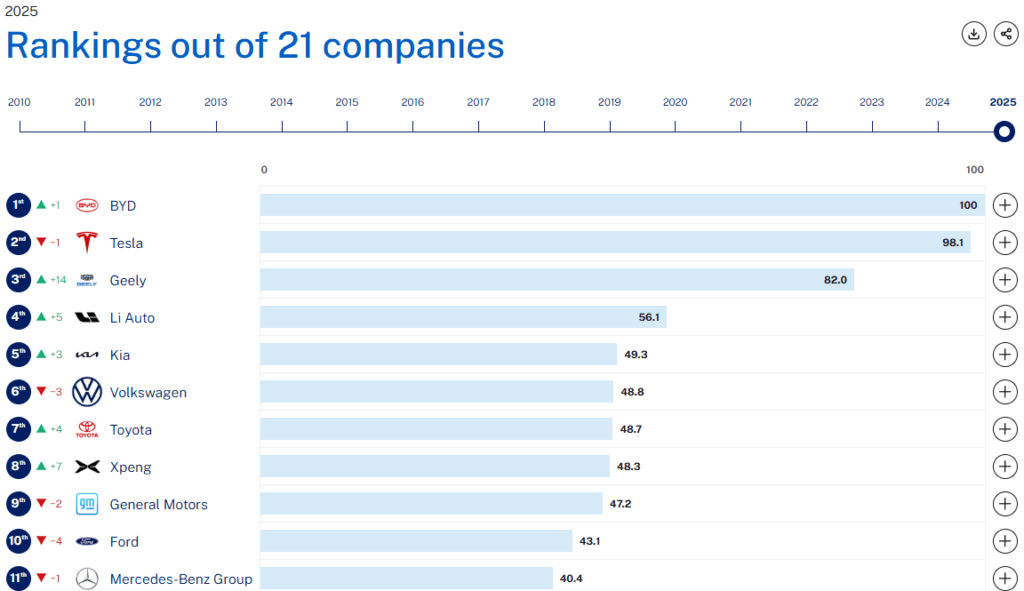
それではトヨタとBYDにどのような差があるかを見ていきます。下のグラフは
1.Stability(経営の安定性)を示すビジネス多様性、財務基盤、投資家からの信頼の領域で、トヨタがダントツに負けているのは、「投資家からの信頼、将来の成長」
2.Innovation(イノベーション)を示すダイバーシティ、R&D、早期結果の創出 という領域では、「ダイバーシティ」がダントツにトヨタが負けている事がわかります
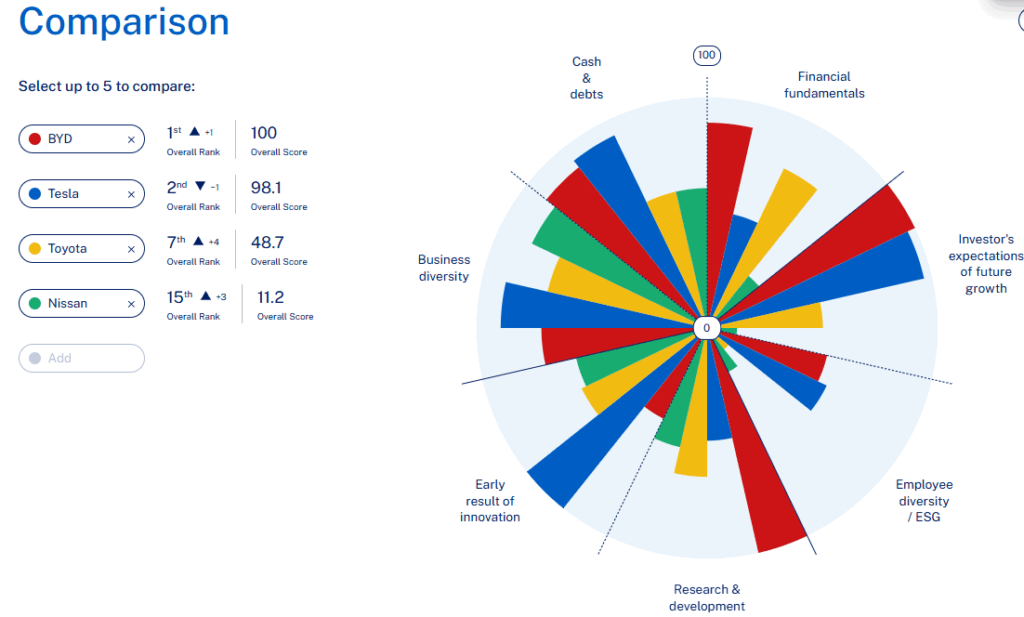
これはトヨタに限った事ではなく、日本企業全般に言える事。
このStabilityとInnovationは、予測し得ない変化が起こっても、それに伴う業績へのダメージを速やかに解決し、対応する力であり、今の企業にはそれらが必要です。
このStability、Innovationの能力を企業として成長させ、アジャイルに物事を判断し、時代の変化に合わせ、新たなプロセス、新たなビジネスを継続的に作り出す企業。それこそが、不確実な中で生き延びていく企業です。
Innovation
先に示したStabilityとInnovationで、では難しいのはどちらでしょう?企業の規模にもよりますが、日本の大企業で考えた場合、既存事業で忙しく、Innovationを起こすことが難しいのではないでしょうか?その為、日本からのイノベーションが30年なく、「失われた30年」言われています。
それではなぜ、日本企業からイノベーションが起こせないのか?
それは、「プラン、アナリシス、コンプライアンス」がオーバーであり、PDCAがPdCaになっている事が原因です。
行動が軽視され、本質をつかんでやり抜く「野性味」がそがれてしまった。
そこに原因があります。
有名なAMDのCEO、Lisa Suの話があります。
Bets and Choices
これを実践して成功を収めた人物。
AMDというと、CPUにかかわる企業という事は、この記事をご覧になっている皆様はわかると思いますが、どちらかというと、Intelの方が有名です。しかし、現在の状況を見てみましょう。
・AMDは、成長を続けているのに対し、Intelは経営資源が分散し、競争力失墜。
なにが起きたのか?
そこに「戦略」という言葉が出てきます。
戦略とは何かを考えてみましょう。
計画を立てること?
違います。よく企業で行われている事業計画。これは戦略でしょうか?
多くの企業が実施している事業計画は戦略ではありません。
戦略に必要な事
・Bets and Choices
そう、戦略とは、何かをして、何かをやめること。
AMDは高性能プロセッサに賭け、そこに投資した。Intelは選択ができず、経営資源が分散し、失墜。
Not knowing for sure is not bad management. It is great leadership
という言葉があります。
すべてを知っているマネージャが優れている時代は過ぎています。不確実な世の中、先のことは誰もわかりません。その中でマネージャは時代を見ながら選択し、野性味を出して実行する、それが今求められているリーダーシップです。
知的創造
Stability、Innovation、Bets and Choices、これらが重要である。といった場合に、次は「どうやって?」という疑問が出てくるのではないでしょうか?
事業を賭け事のようの実行するのは、ギャンブルになってしまい、戦略とは言えません。戦略とは知的創造であり、共感がなければ誰もついてきません。
どのようなプロセスで知的創造をするのか?
どのように共感を得るのか?
そこを書いていきたいと思います。
知識には2つの知識があります。
・暗黙知
・形式知
暗黙知とは、その人だけが知っている、知識、ノウハウ、思い、熱意それらに当たります。
形式知とは、一般化された知識。例えば会社のスローガンであったり、作業手順書だったり。
ここで重要な事は、多くの会社では、暗黙知が多く、形式知化されてない事が多い。という事
共感を得るには、暗黙知から形式知に転換しないと、多くの人との共有が難しい。
という事です。
ビジネスのおける知識とは、新技術、新規ビジネスモデル、新規の業務オペレーションなどです。
そして、あらゆる知識は暗黙知として生まれます。
他者の悩み、課題への共感。それが知識創造の原点となり、暗黙知から形式知に転換し、組織の知識は創造される
有名なSECIモデル。
経験の共感(共同化)→自分の思いを言葉に(表出化)→アイデアの連結(連結化)→実行、振り返り(内面化)
これらプロセスにより知的創造をしていきます。
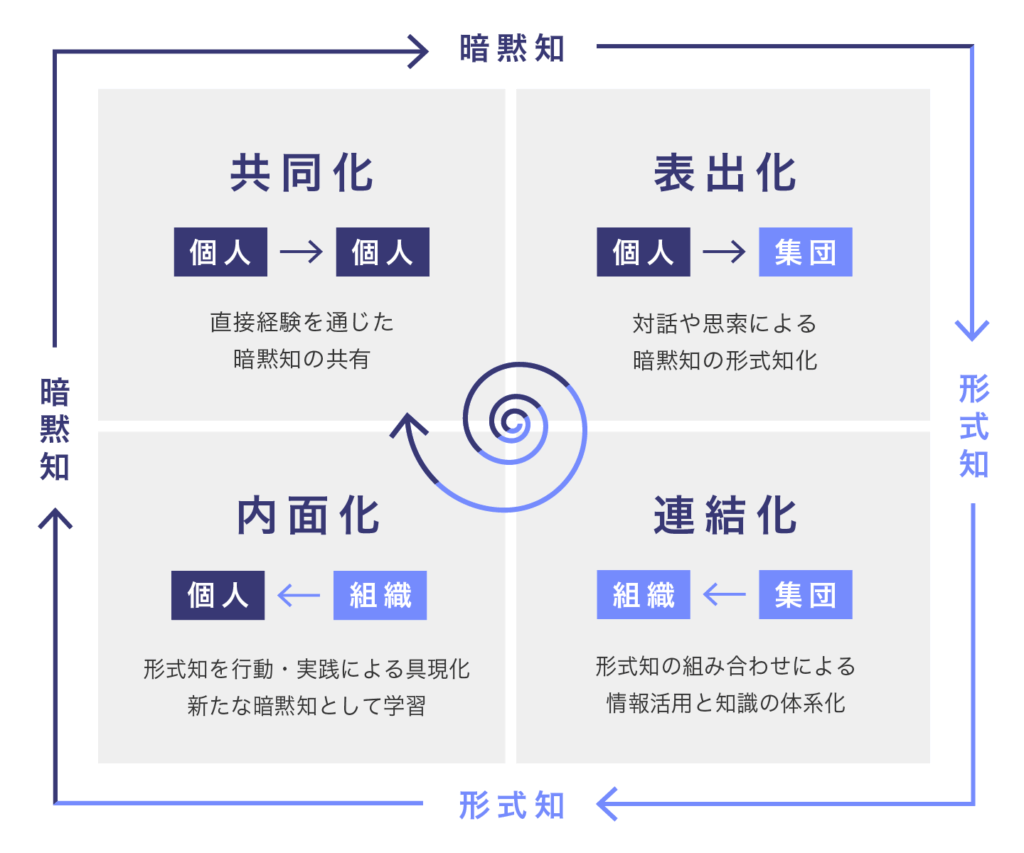
アイデアの種といわれる、各個人が得た暗黙知。何かを生み出す為には、使ってもらうカスタマーのニーズがよく必要といわれますが、ニーズではありません。そのカスタマーの悩み、苦しみ、改善したいところ、そこにメスを入れる必要があります。
それはカスタマーニーズではなく、カスタマーペインです。
ここでいう顧客とは講義な意味で、自分のサービスを使ってくれる人すべてを指します。システムをつくる場合はそのユーザ、自動車を作る場合は、運転手。例えばレポートを作成する場合は、その報告をする先の相手。
私たちが何かを作るとき、それは、ビジネスであれば必ず相手がいます。その相手の悩み、苦しみ、改善したいところ。それがカスタマーペインです。
そして、各個人が得た暗黙知、形式知に変換。
どうやって暗黙知を引き出すか?とある企業が定めたブレインストーミングで定めた1つのルール。
出来そうでなかなかできない、これらのルール。
1.人の話を最後まで聴く
2.トピックから脱線しない
3.突拍子もないアイデアを歓迎する
4.否定しない
5.他社のアイデアへ乗っかる
暗黙知から形式知へ、そしてアイデアの連鎖。現場で知識を生み出す。オフィスの中だけにいては、イノベーションは実現し得ない。
新規事業
事業には2つの進む方向性があります。
・どこで戦うか?
・どうやって勝つか?
どこで戦うか?とは事業領域の事を示し、どうやって戦うか?とは会社の強みの事を指します。
そして定義される領域は次の4領域。
1.既存分野、既存技術
2.既存分野、新技術
3.新規分野、既存技術
4.新規分野、新技術
新規事業とは、1から2,3へ進み、4へ到達する事。
ここで、2,3、4へ進み為に大きな障壁を考えなければいけません。
・技術的障害
・政治的障害
・文化的障害
仕事のやり方を変えることを好まないが故に生じる抵抗を、技術的障害
イノベーションにより、自分の力が弱体化する事を恐れて起こる、政治的障害
過去の経験、慣習の為に起こる抵抗、文化的障害
これらの障害を誰もが感じが事があるのではないでしょうか?
そして、これらの障害の為に、新しい事をあきらめた経験があるのではないでしょうか?
これらの抵抗を乗り越えるために必要な事。
・マネジメントからのサポート
・小さな勝利の繰り返し
・適切な人材の選択
やはり、事業を進めるには、マネジメントからのサポートが必要です。そこの共感を得られなければその先へは進めません。そして、その事業やアイデアを認めてもらうためには、はじめからストレッチな目標を立てるより、小さな目標を繰り返しクリアし、認めてもらうプロセスが重要。
そして最後は、人材。人によって、向き不向きは必ずあります。立ち上げ時に必要な人材、立ち上がったビジネスを継続的に発展させるために必要な人材。それぞれ配置する事。
これらを実施していくことで、各バリアは緩和していくことでしょう。
リーダーシップとは
リーダーシップとは、何でしょうか?
上に立つ人?
偉業を行う人?
特殊能力を持つ人?
どれも違います。
リーダーシップとは、自分らしさを追求する事。
自分らしさ、首尾一貫性、他社・全体善を忘れず、その時々の局面で、全体善と自組織の指名に伴う判断ができる
事を言います。
それには6つの能力が必要と言われています。
1.善を判断できる
2.現実を直視する
3.場を作る
4.本質を語る
5.政治力を行使する
6.他社を育てる
要約すると、良いものをよいと判断でき、現在の状況を正しく判断。コミュニケーションできる雰囲気、人間関係が作れ、その場の中で、正しい事を語り、時には上司の支援を受け、後輩を育てる
どうでしょうか?正しいことを当たり前に実施し、他社と共感しながら進める。非常の当たり前のことです。それを率先してするか、しないか。
リーダーとは自分らしさを発揮するところから始まるもの。それどころか、リーダーのあり方を突き詰める事は、仕事のみならず、「自分らしい生き方」を追求する事につながっている。もしも自分らしさをを大切にしたいのであれば、リーダーになるべき理由に違いない。
自分らしく行動する事で周囲にいい影響を与え、社会をいい方向に導く原動力になる。そんなリーダーとしての生き方を選択肢にするのもよいと思う。

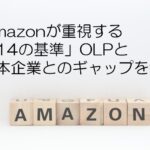
コメント